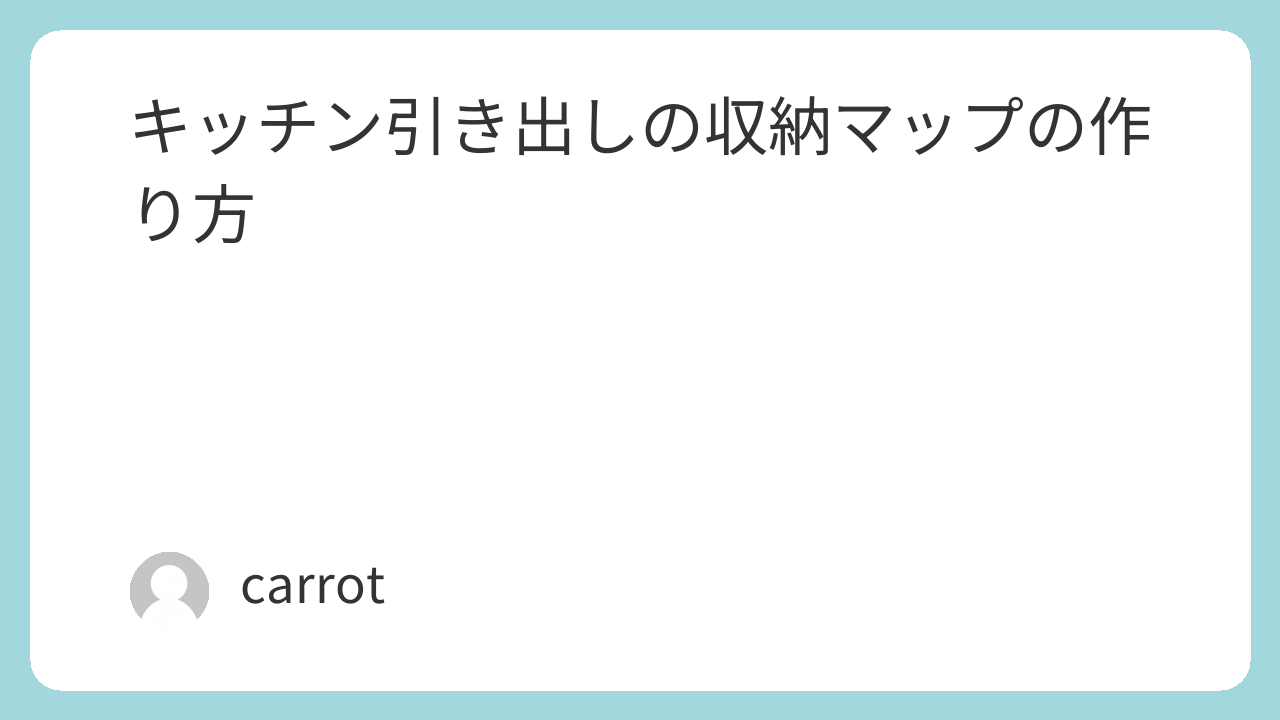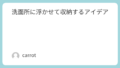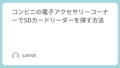あれどこにあったっけ…。こんなモヤモヤした動きに、必ずドキッとするのが「キッチン引き出し」の中。「どこに何が入っているかわからない」この小さなストレスが、毎日の料理を地味に難しくしているのかも。
そんなときに助けてくれるのが「引き出しの使い方を見直す」という発想。とはいえ、やみくもに改造するとよけい混乱するのも実際。
この記事では、キッチンの引き出しをマップ化して、「何が」「どこに」あればいいのかを見えやすくする「キッチン引き出しのマップ」の作り方を簡単に解説します。
スッキリまとまるストレス減らしにも、家族も使いやすいキッチンの助けにも。 「その場しのぐ」にさよならしましょ。
▶「冷蔵庫まわりもスッキリさせたい方には、【冷蔵庫の“見える収納”テク】も参考になります。」
収納マップってなに?必要なの?
「収納マップ」とは、キッチンの引き出しごとに何をどこに入れるかを可視化した、いわば“使いやすさの地図”のようなもの。家の中でも特に物が多くなりがちなキッチンでは、どこに何を置くかが曖昧になりやすく、結果的に探し物や無駄な買い足しが増えてしまうことも。
このマップを作ることで、「どこに何があるか」が一目で分かり、家族との共有もスムーズになります。また、調理中の動線も改善されるので、時短やストレス軽減にもつながるんです。収納上手な人ほど、無意識のうちにこの“収納マップ的な思考”を取り入れているもの。書き出しておくことで、無理なくそれを再現できるようになりますよ。
書き出すだけで見える“使いやすさ”
まずは、現状の引き出し収納の中身をすべて紙に書き出してみましょう。使っている文房具でも、スマホのメモアプリでもOK。大事なのは、「何が」「どこに」あるかを視覚化すること。これだけでも、よく使うものが奥にしまわれていたり、同じようなアイテムがバラバラに収納されていたりする問題点が見えてきます。
たとえば、お弁当グッズが複数の引き出しに散らばっているなら、一つの場所にまとめた方が断然ラク。逆に、使っていない道具が一軍の場所を取っているケースもあるかもしれません。書き出して俯瞰することで、使いやすさを邪魔している要因が明らかになり、収納改善の第一歩が踏み出しやすくなります。
頻度別ゾーン分けのコツ
収納マップを作るうえで、もっとも意識したいのが「使用頻度によるゾーン分け」です。毎日使う道具は取り出しやすい場所に、週1〜2回程度なら中段に、ほとんど使わないものは下段や奥へ。こうして“使用頻度の高い順”に配置を見直すだけで、驚くほど動線がスムーズになります。
たとえば、おたまやフライ返しなどは、コンロ横の引き出しがベスト。お弁当カップやピック類など、たまにしか使わない小物は仕切りケースにまとめて中段へ。来客用の食器や季節限定アイテムは、最下段にまとめておけば普段の作業の邪魔になりません。
このように、使用頻度と行動パターンを組み合わせて収納ゾーンを見直せば、自然と「どこに何があるか」が決まり、日々の調理も気持ちよく進められますよ。
ラベリングと色分けで視覚的に整理
キッチン引き出しの収納マップを作るときに効果的なのが、ラベリングと色分けの工夫です。ラベルを使えば中身がすぐにわかり、家族も迷わず使えるようになります。たとえば「お弁当グッズ」「調味料ストック」「調理ツール」など、使用目的に合わせて引き出しを分類すると分かりやすさがアップします。
色分けは、より視覚的に理解しやすくなるポイントです。たとえばラベルの背景に色を使ったり、引き出しごとにカラーシールを貼ったりすることで、感覚的に「ここは赤=調味料」と認識しやすくなります。とくにお子さんや高齢の家族と共有している場合には、この視覚的な工夫が大きな助けになります。
収納マップ上にもその色を反映しておくと、引き出しを開ける前に目的の場所が一目でわかり、動線の無駄が省けます。日常の動きをサポートする工夫として、ラベリングと色分けはぜひ取り入れてみてください。
家族共有のときに役立つ工夫
キッチンは家族みんなが使う場所。自分だけがわかる収納では、どうしてもモノの位置がバラバラになりがちです。そんなときに役立つのが、家族全員が共通で理解できる収納マップの作成です。
たとえば冷蔵庫の横など、家族の目に入りやすい場所に簡易的な収納マップを貼っておけば、「〇〇どこ?」というやりとりも減ります。また、マップには文字だけでなくイラストや写真を入れることで、直感的に理解しやすくなります。
子どもがいる家庭では、お手伝いを促すツールとしても活躍します。「お箸はここ」「お皿はこの段」と視覚的に教えられると、自分で行動できる機会が増えていきます。家族の自立をサポートする意味でも、共有型の収納マップはおすすめです。
無理せず継続するためのアプローチ
最初は気合いを入れて整えても、時間が経つと元に戻ってしまう…そんな経験、ありませんか?収納マップの継続には、「完璧を目指さないこと」が意外と重要です。
はじめから細かく決めすぎると、逆に管理が面倒になりがちです。そこでおすすめなのは、大まかなカテゴリーで分類し、ざっくりと使いやすさを意識したマップを作ること。たとえば「調理用ツール」「よく使うもの」「ストック類」など、大きなくくりでOKです。
また、月に一度などの見直しタイミングを設けると、現状とズレたままになりにくくなります。家族の暮らし方や季節ごとの使い方の変化にも対応できるので、「続けやすさ」にもつながります。
収納は「生活と一緒に変わっていくもの」ととらえ、ゆるやかに更新しながら付き合っていくのが、長続きするコツです。
キッチン引き出しの収納マップの作り方まとめ
収納マップは、単なる整理術ではなく、毎日のキッチン作業をスムーズにする「生活の味方」です。ラベリングや色分け、家族共有の視点を取り入れることで、誰にとってもわかりやすいキッチンになります。
そして何よりも大事なのは、がんばりすぎずに続けられる仕組みにすること。完璧を求めすぎず、生活の変化に合わせて少しずつアップデートしていくことが、気持ちのゆとりにもつながります。
「どこに何があるかが一目でわかる」。そんな状態が日々の時短やストレス軽減につながるので、まずは気軽に紙とペンでマップを描いてみてください。きっと、新しい発見がありますよ。